Unzip Your Creativity - YKK London Showroom 10 year anniversary video
Director : Mami Kawashima
©YKK Europe Limited.
Motion Graphics
WHAT IS MOTION GRAPHICS?
1997年にグラフィックデザイナーのナガオカケンメイと映像クリエイターの菱川勢一が「動くグラフィックデザイン=Motion Graphics」を定義し《Motion Graphics Exhibition》を開催。グラフィックデザイナーが映像表現を手にしたら。映像クリエイターがデザインを味方につけたら。Motion Graphicsというひとつのジャンルが広がり、新たなクリエイターたちが生まれる産業となることを目指してのことでした。
その後、28年以上の年月が経った今、モーショングラフィックスという名称は広く知られるようになり、無数のMotion Graphicsが発表される一方で、定義や表現がやや曖昧にもなってきました。そんな中、菱川勢一に「Motion Graphicsとは?」を聞きました。
インタビュアー: 小林隆史
Interview
菱川勢一 | Seiichi Hishikawa
photo: Toshimasa Kumagai(DRAWING AND MANUAL)
— 97年に「モーショングラフィックス展」を開催して世界で初めて「Motion Graphics」という名称や定義を発表した後、今は映像分野では当たり前のように使われるようになりました。あらためて、Motion Graphicsとは何ですか?
97年当時、「Motion Graphics」という言葉をパートナーのナガオカから初めて聞いた時に「なにそれ、アニメーションでしょ」って聞き流しました(笑)。
でも、よくよく話をしていって理解したのは、それまで存在していたアニメーションではなく、“動いているグラフィックデザイン”ということだったんです。つまり、映像の中の1フレーム1フレームが、どこを切り取ってもデザインとして成立していること。なるほど、と思いながら同時にこれは世の中に理解されるかなあと心配になったりもしました。
それを「流れるポスター」とか「呼吸するグラフィック」と僕なりに色々と考えたりもしました。
展覧会の目的は、映画監督や専門の映像作家だけの領域だった“映像制作”というフィールドに、グラフィックデザイナーたちが飛び込んでいくきっかけをつくることでした。
当時は「デザイナーが映像?大丈夫?」という声もありましたが、
結果としてそれが、新しい感性と繊細なデザインの産業を生み出す小さな種になった。
いまでは「モーショングラフィックス」という言葉は誰もが知るものになりました。ただ、最近は少し“便利な道具”になりすぎている気もします。
気軽にテンプレートを動かせば、たしかに“動くもの”はできます。
でも、本当のモーショングラフィックスとは、フレームのひとつひとつに「思想」や「美意識」が宿ってこそなんですよね。
モーショングラフィックスは「手段」じゃなくて「詩」なんだろうなあとか。
効率よりも、ちょっとした遊び心や間の美しさ。
そこに、まだ伸びしろがあると思っています。
Motion Graphic Works
-

Unzip Your Creativity
YKK London Showroom 10 year anniversary videoNew List Item
-

ap bank fes ’25
apbank
-

132 5. ISSEY MIYAKE
Brand Images
-

日本酒を創り、潤すまでの道のり
阿武の鶴酒造
-

MIYOSHI - JAPANESE SAKE
阿武の鶴酒造
-
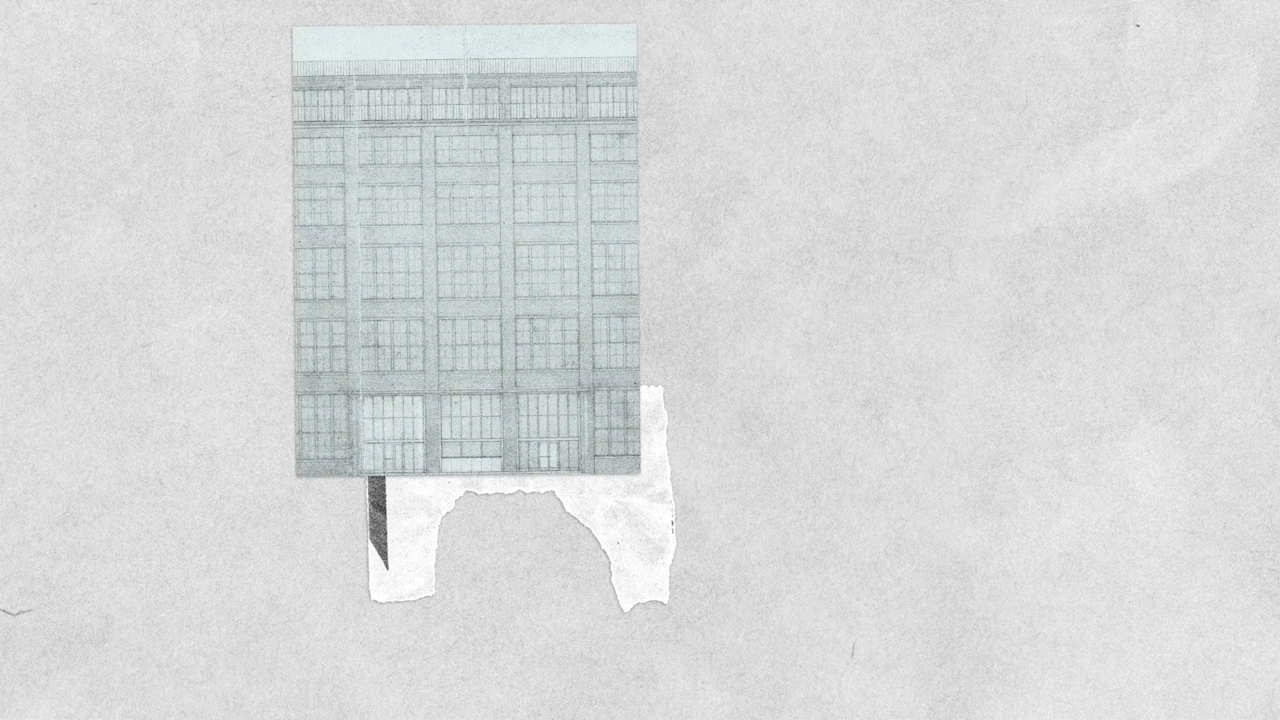
JP TOWER OSAKA
KITTE OSAKA
-

スピード|Helsinki Lambda Club
MV
-

GNIBN Ⅱ(feat. PEAVIS, CHAI) |Helsinki Lambda Club
MV
-

トロトロレトロちゃん
TV TOKYO『シナぷしゅ』
-

さんごdeタンゴ
テレビ東京『シナぷしゅ』
-

smart
Mercedes-Benz
-

発酵ものがたり
カルピス
Motion Identity Works
-

UNIVERSAL MUSIC GROUP
Motion Identity
-

KADOKAWA PICTURES
Motion Identity
-

RECRUIT
Motion Identity
-

Blue Marble
Motion Identity
-

Sony Ericsson
Motion Identity
-

SWFC
Motion Identity

